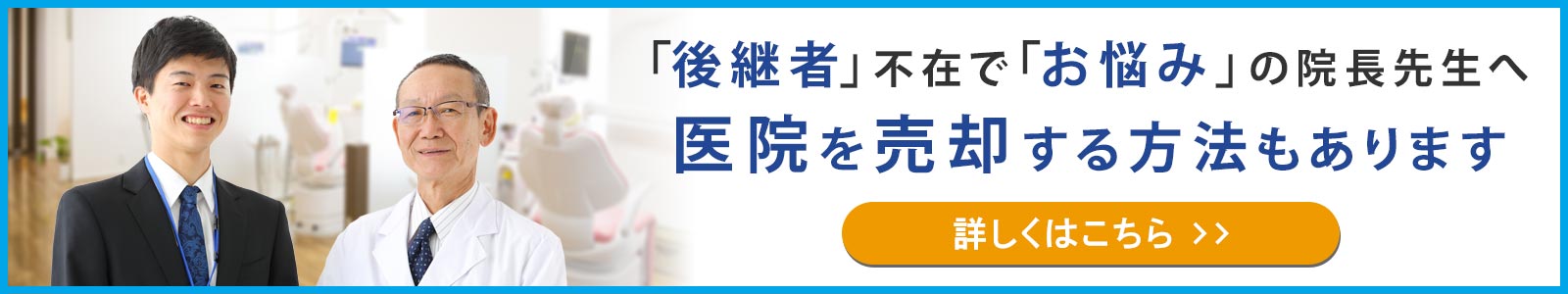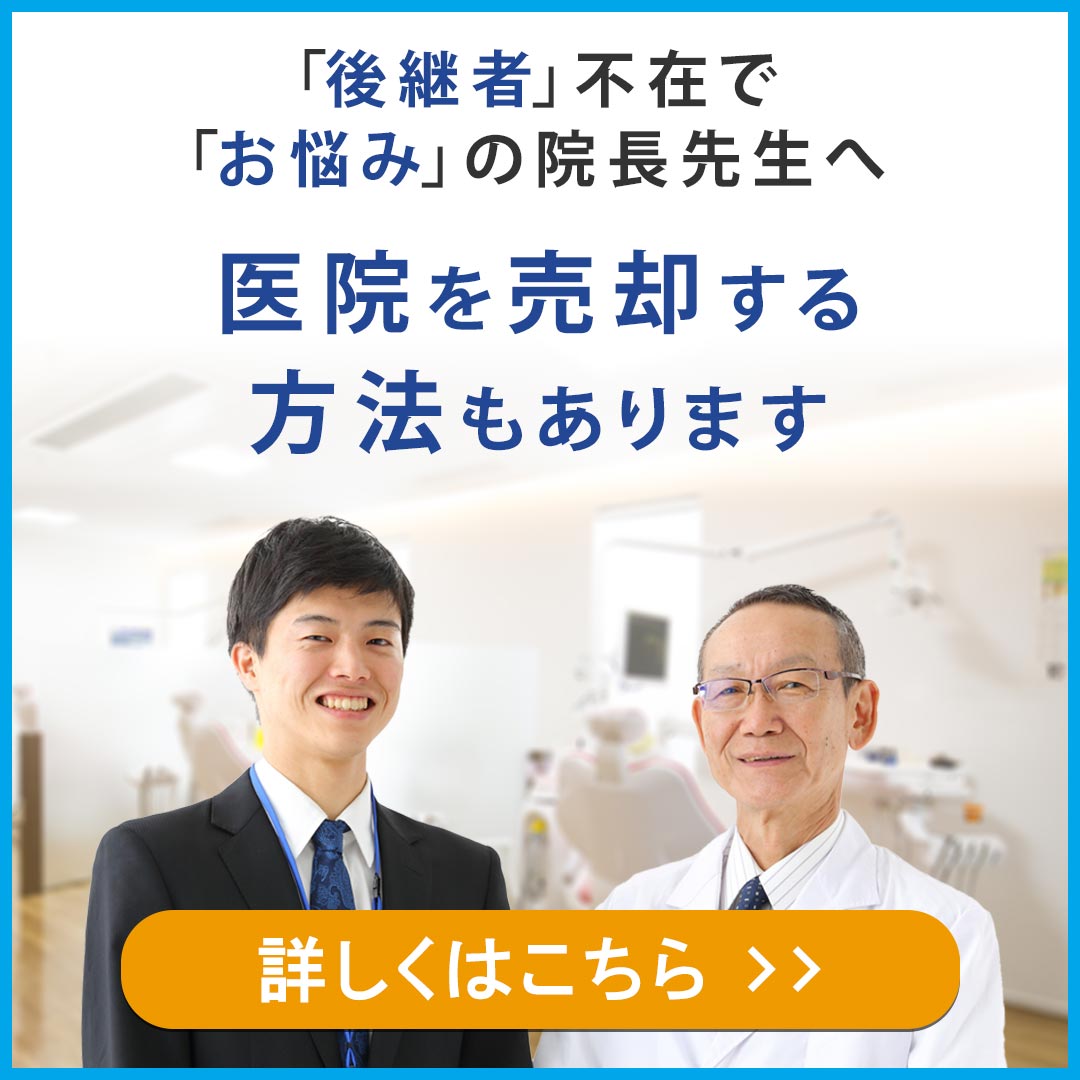「最近、患者さんが来なくて、空き時間ばかりが増えている…」
そんなお悩みを抱える院長先生に向けて、本記事ではご自身の医院で取り組める見直しのポイントを整理し、患者さんを増やすためのヒントをご紹介します。
すでにネットや書籍などで患者を増やす方法について調べているかもしれません。
しかし、「ネット広告を出す」「SNSを活用する」といった方法を試してみたものの、「思うような結果が出なかった」と感じている先生も多いのではないでしょうか。
患者を増やす方法に、すべての医院に共通する「これが正解」といったものはありません。
それぞれの医院が持つ立地や設備、診療内容、スタッフ体制などの“前提条件”を踏まえた上で、自院に合った方法を考える必要があるのです。
本記事では、「立地× 診療 × 人 × 設備」という4つの視点から、それぞれの医院に合った現実的な対策を一緒に考えていきます。
他院の成功例が通用しない理由と自院に必要な考え方
「この方法で患者が倍増!」 そんな成功事例を目にすると、つい「うちでもやってみよう」と思ってしまいがちです。
ですが、実際にその方法がうまくいったのは、その時期の地域環境や競合状況、医院の特徴と偶然かみ合っただけというケースも少なくありません。
つまり、“その医院だからこそ成功した”という背景があるのです。
歯科医院はそれぞれ、立地、患者層、診療方針、設備、人柄など、条件が大きく異なります。例えば、
- 駅前にある医院と郊外の住宅地にある医院では、来院動機も時間帯も違います
- 若年層が多い地域と高齢者が多い地域では、求められる診療内容や接し方も変わります
- 新規開業の医院と、地域密着型で20年続く医院では、アプローチの仕方も当然異なります
他院の成功例はあくまで参考程度にとどめ、自院の強みや課題に向き合った対策を考えることが、実は一番の近道です。
大切なのは、「うちの医院が、どのような患者さんに、どのように見られているか」を冷静に見つめ直すこと。
そのうえで、場所・診療内容・スタッフ対応・設備といった“自院ならでは”のポイントを磨いていくことが、長く安定して患者に選ばれる医院づくりにつながります。
立地タイプ別|医院の場所によって変わる戦略
ビジネス街:ネット告知強化と「時間厳守」の姿勢がカギ

ビジネス街では、昼休みや仕事帰りに立ち寄るビジネスマンやOLが中心となります。
そのため、「短時間で終わる」「予約が取りやすい」「昼休みも診療可」といったスピードと利便性が強く求められます。
加えて、ビルや商業施設内に入っている医院が多いため、看板などによる通行人へのアピールが難しい問題があります。
通勤者の多くは、駅から勤務先までの決まった通勤ルート上にある店舗しか目に入りません。
ルートから外れた場所にある歯科医院が、看板をきっかけに認知されることは、ほとんど期待できないのが実情です。
そのため、ネット上での認知獲得が重要になります。具体的には、以下の施策を強化・見直すと効果的です。
- ホームページ(SEO対策や駅からの写真付き道順の明記)
- Googleビジネスプロフィールの情報充実とクチコミ管理
- Google広告(地図連動や「駅名+歯科」のキーワード)
特に昼休みに来院する患者は「遅刻したら仕事に支障が出る」と考えるため、診療の待ち時間や所要時間が不透明だと、避けられる要因になります。
時間通りに始まり、予定通りに終わるようきちんと段取りを整えることが大切です。
以上の点を意識して、ビジネス街での医院運営・情報発信を行うことが、患者数の安定につながります。
駅前:差別化と“分かりやすいアクセス案内”が決め手

駅前は人通りが多く、利便性の高いエリアですが、その分歯科医院が密集している“激戦区”でもあります。
患者にとっては「駅から近い医院がたくさんある」状態であり、「選ばれる理由」が明確でなければ、他院に埋もれてしまうリスクが高いのが実情です。
このような環境では、「アクセスの良さ」だけでは差別化になりません。
治療方針、診療メニュー、医院の雰囲気、タッフの対応、診療時間の柔軟さなど、患者が比較したときに「ここに通いたい」と感じてもらえる明確な特徴を打ち出すことが重要です。
特に、次のような点を確認してみましょう。
- 他院では対応していない診療(例:ホワイトニング・短期集中治療など)
- 働く世代に配慮した早朝・夜間診療の柔軟さ
- 院内の雰囲気・清潔感・話しやすさなどの“通いやすさ”
加えて、実際の場所の“分かりやすさ”も来院率に大きく影響します。
ビルの2階以上や、細い路地の奥などにある場合、患者は見つけづらさから知られていない可能性があります。
Googleマップをしっかり管理しているか、経路案内で迷わないかを必ずチェックしましょう。
駅周辺という立地の利点を活かすには、「数ある中から、なぜこの医院なのか?」という問いに明確に答えられる設計が必要不可欠です。
住宅街:地域密着と家族対応で信頼と口コミを育てる

住宅街にある歯科医院は、地域に住む住民が長く通う“生活に根ざした医院”としての役割が求められます。
そのため、患者との信頼関係や安心感が来院動機になりやすく、広告よりも口コミ・紹介が来院のきっかけとなるケースが多いのが特徴です。
このようなエリアでは、「家族で通えるかどうか」「小さな子どもや高齢者にも優しいか」といった視点が重要になります。
具体的な取り組みとしては、以下のような点を見直してみましょう。
- 子ども連れでも安心できるキッズスペースや、ベビーカー対応の院内設計
- 年配の方でも来院しやすいバリアフリー対応や段差解消
- 衛生士や受付が患者の名前や顔を覚えることで「親しみ」を演出
- 受付や電話対応において、言葉遣いやトーンを温かく丁寧にする
住宅街で安定した患者数を維持するには、“診療の質”だけでなく、“関係性の構築”も大変重要です。
目の前の患者を丁寧に診ることで、その家族や友人にも自然と広がっていく、そんな「じわじわと効く集患の流れ」を作っていくことが、住宅街型の医院にとって最も有効なアプローチといえるでしょう。
郊外・ロードサイド:親しみやすさと安心感の積み重ねが決め手

郊外やロードサイドに位置する歯科医院では、車を使う高齢者も多く、小さな子どものいる家庭も含め、家族全員が長くお付き合いできそうか、通いやすい医院かどうかが問われます。
以下のような工夫が、患者満足度と定着率の向上につながります。
- 駐車場から医院に入るまで、バリアフリー対応か
- 高齢者でも安心な手すり・段差対策
- 小さなお子さん連れでも安心できる院内対応(柔らかい雰囲気・優しい声かけ)
- 衛生士・受付スタッフが患者との雑談をメモして次回来院時の会話に生かす
- 定期検診やメンテナンスの提案を、家庭単位で丁寧に案内する
また、郊外では他の医院との比較材料が少ない分、「一度できた信頼」は長く継続しやすいという特徴があります。
逆に言えば、一度でも不信感を与えると、その印象も地域に広がりやすいという側面もあるため、初診対応やクレーム時のフォローには特に慎重さが求められます。
郊外型医院の強みは、都市部にはない“人とのつながりの濃さ”にあります。
無理に集患を急ぐのではなく、目の前の患者一人ひとりを丁寧に対応することで、確実に患者が“自然に増えていく”仕組みを築くことが大切です。
診療内容別|治療メニューによって変わる集患施策
審美・インプラント中心:信頼と症例紹介で患者の不安を解消

審美歯科やインプラントなどの自由診療を中心とする歯科医院では、「患者に信頼してもらえるかどうか」が集患と成約の成否を大きく左右します。
都心でも郊外でも、高額治療に対する患者側の心理には共通点があり、「本当にこの医院に任せて大丈夫か」「高い費用を払って後悔しないか」といった不安をいかに解消するかが重要です。
サイトに豊富な症例を掲載し、安心と納得を与える
自由診療では特に、過去の実績=症例紹介が信頼につながります。
「自分と同じような悩みを持っていた人が、どのように治療され、どう変わったか」が具体的に分かれば、患者は「自分も安心して治療を任せられそうだ」と感じやすくなります。
そのため、ホームページには以下のような工夫が有効です。
- ビフォー・アフター写真を多数掲載(同意が取れた範囲で)
- 症例ごとに年齢・性別・主訴・使用した素材・費用・治療期間を記載
- 写真だけでなく、患者の声・感想・治療の流れをテキストでも補足
- 「前歯の見た目が気になる方へ」「インプラントかブリッジか迷っている方へ」など悩みに合わせた説明の“入り口”を作る
これにより、単なる技術の自慢ではなく、患者に寄り添った提案をしている医院であるという印象を与えることができます。
高額治療だからこそ「支払い時の安心感」が信頼につながる
近年、自由診療を巡っては、一括前払いをした後に医院が突然閉院してしまい、患者が被害を受けるといったトラブルも報道されています。
こうした事例を知っている患者ほど、治療費の支払いには慎重になっています。
そのため、医院側としても次のような「不安を解消する仕組み」をあらかじめ提示しておくことが効果的です。
- 一括前払いを避け、治療の進行段階ごとに分割して支払う方式を案内する
- 金融機関のデンタルローンを紹介する場合でも、「契約前に治療計画を丁寧に説明する」ことを徹底
- キャンセル時の返金規定なども明示しておく(トラブル防止と信頼感の両面)
こうした配慮は患者にとって大きな安心材料となり、治療を前向きに検討する後押しとなります。
自由診療こそ、価格よりも“信頼”が決め手になる
自費診療では、値段だけを比較されることはあまりありません。
それよりも「症例の豊富さ」「説明の丁寧さ」「医院の安定感」「院長やスタッフの人柄」といった“信頼できそうかどうか”が決め手になります。
そのため、ホームページやカウンセリング時には以下のような意識が大切です。
- 難しい言葉を使わず、患者目線で丁寧に説明する
- 押しつけではなく、複数の治療法を提示して選択してもらう
- 実績や症例を見せながらも、「あなたにとって必要かどうか」を一緒に考える姿勢を示す
このように、信頼と安心感を丁寧に積み上げることで、患者の不安は自然と和らぎ、結果的に選ばれる医院へとつながっていきます。
治療中の強引な自費提案は逆効果 : 患者の納得が最優先
虫歯治療の最中や、歯を削った直後の段階で、高額なセラミック治療などの自由診療を強く勧める医院も一部に存在します。
いわゆる「治療の途中で、患者が断りにくいタイミングを狙って自由診療を提案する」という形です。
こうした提案は、患者側にとっては「断りにくい状況で非常に弱い立場=まな板の鯉状態」に置かれた中での決断となるため、一見その場で契約が成立したとしても、あとから強い後悔や不信感につながるリスクがあります。
特に気の弱い方や、高齢者などは、「いま断ったら、この後の治療はちゃんとしてくれるのだろうか」と感じてしまい、本心では納得していないまま契約に進んでしまうケースも少なくありません。
こうした対応は、以下のような重大なデメリットを生みます。
- 後日、知人や家族に相談した際に不信感を強めてしまう
- SNSや口コミサイトで「無理に高額治療を勧められた」と書かれてしまう
- 患者の信頼を失い、再来院が見込めなくなる
医院経営の観点から見ても、短期的な利益のために信頼を損ねるのは大きな損失です。
患者の数をただ“増やす”ことではなく、「納得して治療を受けてくれる患者を増やす」ことが、長期的な発展に繋がるのです。
そのためには具体的には、以下のような配慮が必要です。
- 自由診療の提案は、治療を始める前のカウンセリング時に行う
- 保険診療と自費診療の違い、費用、見た目、耐久性などを丁寧に比較して伝える
- 選択肢を提示した上で、最終的な判断を患者自身に委ねる
自由診療は、医療機関の収益を支える大切な柱ですが、信頼と納得の上に成り立ってこそ、継続的な選ばれる医院づくりが可能になります。
目先の利益ではなく、患者目線での誠実な提案こそが、口コミ・紹介・リピートに繋がる“本当の成長戦略”と考えましょう。
保険中心の医院は、スタッフ対応と再来院率向上がカギ

保険診療をメインとする歯科医院では、高額な自由診療に頼ることが難しい分、日々の診療数と再来院率が経営の安定を左右します。
つまり、「一人ひとりの患者さんが、継続して通ってもらえるかどうか」が非常に重要になります。
このような医院においては、派手な集患施策よりも、日常の診療や対応の中で信頼を積み重ね、リピートを生み出すことが最も効果的な集患策となります。
医院への印象が、継続通院の決め手になる
保険診療では、治療費に大きな差が出ないため、患者は「医院の対応」や「通いやすさ」で継続の判断をします。
具体的には、次のようなポイントを押さえることが重要です。
- 受付の挨拶や対応が丁寧である(電話応対も含む)
- 医師・衛生士ともに説明が簡潔でわかりやすい
- 初診の方には「また来たい」と思ってもらえる雰囲気づくり
特に受付や衛生士の対応が温かく、表情や声かけに安心感がある医院は、患者にとって「長く通いたい場所」になります。
院長先生の中には、受付の対応や人当たりの良さをそれほど重視されていない方もいらっしゃいます。
しかし実際には、受付が不愛想だったり説明が不十分だったりするだけで、来院をためらい離れてしまう患者さんは意外と多く存在します。
定期検診と再来のしくみ設計
患者に「また行こう」「定期的に通わなきゃ」と感じてもらえる流れを作ることは、医院経営の安定において非常に重要です。
とくに歯石除去などのメンテナンス目的で継続的に通ってもらうには、患者本人がその重要性を“自分ごと”として理解・実感していることが欠かせません。
そのための一つの工夫として、歯石の付着状況を実際に見せたり、取り除いた歯石を処置後に見せたりすることで、「こんなに付いていたのか」と実感してもらうという方法があります。
視覚的に確認できることで、日頃のセルフケアだけでは不十分であることに気づき、定期的な来院の必要性を納得してもらいやすくなります。
また、歯石除去を怠ることで、
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)のリスクが高まること
- 進行すれば将来的に入れ歯になる可能性もあること
など、長期的なリスクを“あらかじめ”伝えておくことも、継続通院へのモチベーションづけとして非常に効果的です。
このようにして、定期的な来院の必要性とその理由を明確に伝えることができれば、患者は「自分のために通う」という意識を持ちやすくなります。
人の印象が良い医院は、「また来たい」と思われる

どんなに治療の技術が高くても、どんなに設備が整っていても、患者さんが最初に接するのは“人”です。
受付・衛生士・院長、誰とどのように接したかという印象が、「この医院にまた通いたい」と思えるかどうかを大きく左右します。
特に初診の段階では、患者は不安を抱えて来院しています。
そこで対応したスタッフが冷たかったり、説明が不十分だったりすると、「感じが悪かった」という印象だけが残り、再来院につながりません。
逆に、特別なサービスをしていなくても、
- 受付が笑顔で迎えてくれた
- 衛生士が気さくに話しかけてくれた
- 院長が落ち着いて説明してくれた
といったちょっとした対応が、「安心できた」「話しやすかった」という印象につながり、患者の再来院や家族への紹介に結びつきます。
院長がいくら丁寧でも、受付や衛生士の対応が冷たいと「感じの悪い医院」という印象になってしまいます。
反対に、スタッフ全体が穏やかで親しみやすい対応を心がけていれば、「安心して通える医院」として患者の記憶に残ります。
「人の印象が良い医院は、また来たいと思われる」というのは、どんな医院にも共通する重要な要素です。
設備・建物が与える影響とは?

新しく開院する歯科医院は、内装も外観もきれいで洗練されており、それと比較すると、開業から何十年も経過した医院はどうしても古さや見劣りを感じさせてしまいます。
だからこそ、築年数ではなく“清潔感”や“居心地の良さ”で勝負する姿勢が重要です。
年数を重ねた医院では、待合室に注意書きや案内などの張り紙が次第に増えていく傾向があります。
しかし実際には、多くの患者はそれらを読んでおらず、むしろ雑然とした印象を与える原因になってしまいます。
特に壁やガラスにベタベタと貼られた張り紙は、「古い」「ごちゃごちゃしている」と感じられやすく、思い切って一度すべて外してしまうくらいがちょうど良いケースもあります。
また、待合室のイスやソファーが破れていたり、テープで補修されていたりする状態も、医院全体の印象を大きく損ないます。
ニトリやIKEAなどで市販されている一人掛けの椅子に取り替え、整然と並べるだけでも、待合室の印象は大きく向上します。
このように、大掛かりなリニューアルをしなくても、医院を丁寧に見直すだけで“古くても清潔感のある医院”を演出することは十分可能です。
患者が最初に感じるのは“築年数”ではなく、“清潔感と快適さ”であることを意識しておくとよいでしょう。
まとめ|自分の医院に合った“増やし方”こそ、最大の近道

「患者が来ない」という悩みは、単なる“集客不足”ではなく、医院全体の見直しポイントのサインでもあります。
本記事で紹介したように、場所・診療・人・設備という4つの視点で整理すれば、自院が取り組むべき具体的な方向性が見えてきます。
万能の解決策はありませんが、医院の特徴に合わせて“強みを活かす工夫”をすれば、無理なく状況を改善していくことは十分に可能です。
![バートンオフィス株式会社[先生の意思を引き継ぐお手伝いをご一緒に]](/img/barton-logo.svg)